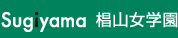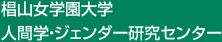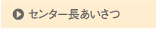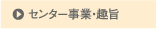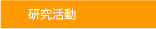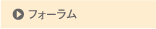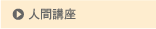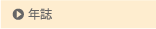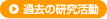人間学・ジェンダー研究センターでは、新たな人間についての知の開発を目指し、様々なプロジェクト(研究活動)を進めております。ここでは、当センターにて取り組んでいる研究テーマと内容を記載しています。旧年度の研究活動については、本ページ下部のリンクにより参照できます。
■人間学・ジェンダー研究センター研究組織
| センター長 | 加藤 泰史 | |||
| 主任研究員 | 杉藤 重信 |
■「AI時代の人間観の転換」プロジェクト
カント以降の近代的人間観を再検討しながら、AI革命以前の現代的人間観をアーレントに即して検討すると同時に、これらの考察を踏まえてAI革命以後の人間観がどのように転換したのかを明らかにします。カントの人間観、アーレントの人間観、惑星倫理学、生成AIの諸観点)を踏まえて、論点を総合し、現代的人間観の転換を明らかにして「人間になろう」の新たな意味づけを探っていきます。
| 代 表 | : | 加藤 泰史 | 人間学・ジェンダー研究センター長、 | |
| 椙山女学園大学外国語学部教授 | ||||
| 三浦 隆宏 | 椙山女学園大学人間関係学部教授 | |||
| 立花 幸司 | 千葉大学大学院人文科学研究院准教授 | |||
| 戸谷 洋志 | 関西外語大学英語国際学部准教授 |
■「人と自然の関係をめぐる学際研究を通じた「人間学」の探求」プロジェクト
「人新世」と呼ばれる現代では、人間中心主義の自然観を脱却し、人と自然の関係を根本から問い直し、新たな人間像の構築が求められています。そのためには「人間/自然」の二元論を克服し、学問分野を超えた幅広い視座が不可欠です。本プロジェクトは、このような幅広い視座を取り入れた自然科学と人文科学を統合した学際的な研究によって、人と自然が織りなす関係を多面的に描くことを目的とします。
| 代 表 | : | 松浦 直毅 | 椙山女学園大学人間関係学部准教授 | |
| 五百部 裕 | 椙山女学園大学人間関係学部教授 | |||
| 横山 拓真 | 人間学・ジェンダー研究センター特別研究員 | |||
| 仲澤 伸子 | 椙山女学園大学大学院人間関係学研究科特別研究員 | |||
| 木村 大治 | 京都大学名誉教授 | |||
| 二文字屋 脩 | 愛知淑徳大学交流文化学部准教授 |
■「幼児教育における性の多様性を尊重する教育実践に関する研究」プロジェクト
本プロジェクトでは、性の多様性に配慮した幼児教育段階におけるジェンダー教育プログラムを調査研究することを通して、幼児期のジェンダー教育の指針について提案することを目的としています。そのために、次の3点を通して研究を進めます。①「幼児教育におけるジェンダー教育および性の多様性教育の実践に関する課題を整理」、②「海外の教育実践事例に関する文献調査」、③「保護者へのインタビュー調査を実施し、課題を整理」
| 代 表 | : | 藤原 直子 | 椙山女学園大学人間関係学部教授 | |
| 伊藤 博美 | 椙山女学園大学教育学部教授 | |||
| 虎岩 朋加 | 椙山女学園大学人間関係学部教授 |
■公募プロジェクト
日本の地方議会は女性議員の割合が自治体別で大きく異なることに注目し、近年女性の社会進出が活発化している愛知県内の自治体を取り上げ、なぜ女性議員が増えたのかを文献調査やインタビュー調査を行い、愛知県内の市議会での女性議員増加の実態や要因を明らかにすることを目的とします。
| 代 表 | : | 大木 直子 | 椙山女学園大学人間関係学部准教授 |
ご注意:掲載文書はPDF形式になっていますが、あなたのコンピュータに最新のAdobe Readerがインストールされていない場合でも表示されます。しかし、ファイルサイズによって時間がかかる場合があります。しばらくお待ち下さい。
以下のプルダウン・メニューから表示する年度を選択してください。